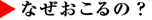

地球温暖化とは、人間活動の拡大により二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素などの温室効果ガスの大気中の濃度が増加し、地表面の温度が上昇することをいいます。IPCC(気候変動に関する政府間パネル)の報告によれば、温室効果ガスの濃度が現在の増加率で推移した場合、21世紀末までに地球全体の平均気温が2℃上昇することがありうるとしています。
・太陽から届く日射エネルギーの7割は、大気と地表面に吸収されて熱に変わります
・地表面から放射された赤外線の一部は大気中の温室効果ガスに吸収され、地表を適度な温度に保っています
・人間活動により、大気中の温室効果ガスの濃度が急激に上昇しています。そのため、これまでのバランスを越えて赤外線が温室効果ガスに吸収され、その結果、地表の温度が上昇してしまいます
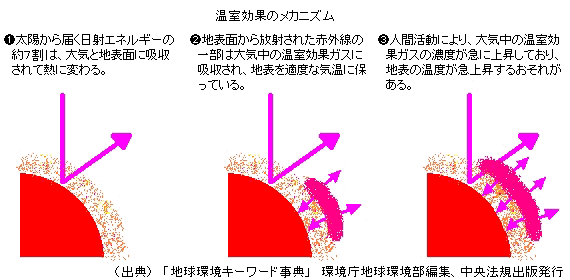
温室効果ガスにはさまざまな物質がありますが、主なものとして次の5つが知られています。


現在得られている知見によると、大気中の二酸化炭素濃度は

に達しています。他の温室効果ガスの大気中濃度もおおむね二酸化炭素より大きく増加しています。そして、このまま二酸化炭素の放出が続くとその温度は21世紀末には産業革命以前の2倍近くに達すると考えられています。
この温室効果ガスの増加による平均気温の上昇で考えると、21世紀末には世界平均で約2℃上昇することが示されています。地域的にはさらに大きな上昇が予測されています。
また、海面水位の上昇で考えると、21世紀末までに約50センチに達するとの予測が示されています。
急激な気温の上昇による影響として
など、地球環境と私たちの生活に甚大な被害が及ぶものと考えられます。
このように、地球温暖化の問題は、非常に広範囲・長期間にわたって地球環境への影響が考えられ、また、すぐに目に見える形で影響が表面化しないものでもあり、これまでの局地的な環境問題とは大きく性格の異なる現象です。私たちも地球温暖化の問題を、自分の子や孫の将来世代のことを見通して理解していく必要があります。
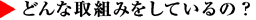
1988年11月にUNEPとWMOの共催により、地球温暖化に関する科学的側面をテーマとした初めての公式の政府間の検討の場として設置され、世界の専門家や行政官が中心となって、地球温暖化の科学的知見、環境的・社会経済的影響、対応戦略について検討が行われ、国際的対策の進展に合わせ政府決定者に対し、最も信頼できる科学的・技術的知見を提供しています。
1989年11月にオランダのノールトヴェイクにおいて開催された「大気汚染と気候変動に関する環境大臣会議」で採択された宣言で、温室効果ガスの排出量を安定化させる必要性が初めて認識されたものとなっています。
1990年12月に国連内に設置された同条約の交渉会議により検討が開始され、1992年5月に条約が採択されました。この条約は、同年の地球サミットの開催期間中に日本を含めた155カ国が署名を行っています。その後、地球温暖化問題への各国の関心の高さを反映して、1997年5月時点での締約国は167カ国に至っています。
気候変動に関する枠組み条約の概要は次の通りです。
|
○先進国における約束(コミットメント) |
|
|---|---|
| ・ | 温室効果ガスの排出・吸収の目録作り |
| ・ | 温暖化対策の国別計画の策定と実施 |
| ・ | エネルギー分野などでの技術の開発、普及 |
| ・ | 森林などの吸収源の保護・増大対策推進 |
| ・ | 科学、調査研究・計測などの国際協力 |
| ・ | 情報交換、教育・訓練などの国際協力 |
| ・ | 条約の実施に関する情報の通報など |
| ・ | 温室効果ガス排出量の1990年代末までの従前レベルへの回帰 |
| ・ | 温室効果ガス排出量の1990年レベルへの回帰を目指した政策・措置の情報提供 |
| ・ | 途上国への資金、技術の支援(旧ソ連、東欧諸国については免除) |
|
○途上国における約束(コミットメント) |
|
| ・ | 温室効果ガスの排出・吸収の目録作り |
| ・ | 温暖化対策の国別計画の策定と実施 |
| ・ | エネルギー分野などでの技術の開発、普及 |
| ・ | 森林などの吸収源の保護・増大対策推進 |
| ・ | 科学、調査研究・計測などの国際協力 |
| ・ | 情報交換、教育・訓練などの国際協力 |
| ・ | 条約の実施に関する情報の通報など |
地球温暖化問題に対する取組の経緯
|
|
|
|
| 1990年8月 | IPCC第1次評価報告 | |
| 1990年10月 | 「地球温暖化防止行動計画」策定 | |
| 1992年6月 | 地球サミットの開催→条約が署名のために開放 | |
| 1993年5月 | 条約の受諾 環境基本法制定 |
|
| 1994年3月 | 条約の発効(3/21) | |
| 1994年11月 | IPCC特別報告書 | 「環境基本計画」策定 |
| 1995年3月 |
第1回締約国会議(COP1)(ベルリン) 2000年以降の先進国の取組についての議定書等を97年中に取りまとめることを決定(ベルリン・マンデート) |
|
| 1995年6月 | 「国の事業者・消費者としての環境保全に向けた取組の率先実効のための行動計画」策定 | |
| 1995年8月 | AGBM(ベルリンマンデート・アドホックグループ)第1会会合 | 「21世紀地球環境懇話会」設置 |
| 1995年10月 | AGBM2 | 気候変動に関する世界自治体サミット(埼玉) |
| 1995年12月 |
IPCC第2次評価報告書 人間活動の影響による地球温暖化が既に起こりつつあることが確認され、温暖化の進行を止めるには、温室効果ガス排出量を将来的に1990年を下回るレベルまで削減する必要がある等、新たな知見を整理し、「後悔しない対策」を超えた対策を開始する根拠があるとした。 |
|
| 1996年1月 | 地球温暖化アジア太平洋地域セミナー(仙台) | |
| 1996年3月 | AGBM3 | |
| 1996年4月 | 目録(CO2その他の温室効果ガス)送付 | |
| 1996年5月 | 国連持続可能な開発委員会(CSD第4回会合) |
「地球温暖化を防ぐ4つのチャレンジ」の推進を提唱 (「環境家計簿」「グリーン・オフィス、エコ商店」「1日1万歩」「アイドリング・ストップ」 COP3我が国招致に関する閣議了解 |
| 1996年7月 |
AGBM4 COP2(ジュネーブ) 法的拘束力のある数量目的を含みうる新たな法的文書に向けた交渉の加速化等を内容とする閣僚宣言を表明。COP3の日本開催を決定。 |
|
| 1996年11月 |
地球懇地球温暖化問題特別委員会の報告書取りまとめ、公表 地球温暖化アジア太平洋地域セミナー(フィジー) |
|
| 1996年12月 | AGBM5(我が国としての議定書案を提出) | |
| 1997年3月 | AGBM6 | 地球環境パートナーシップ会議 |
| 1997年4月 | 第2回国別情報通報期限 | |
| 1997年6月 | 国連環境特別総会 G7サミット | 「エコライフ100万人の誓い」運動の展開 |
| 1997年12月 | COP3(京都) | |
| 1997年12月 | 先進国全体として、2008年から2012年までの間に温室効果ガスを少なくとも5%削減するよう義務づける「京都議定書」を採択 | 「地球温暖化対策推進本部」を内閣に設置 (地球温暖化防止に関わる具体的かつ実効のある対策の総合的な推進) |
| 1998年1月 | 「地球温暖化対策推進本部」第1回会合 | |
| 1998年3月 | 「今後の地球温暖化防止対策のあり方」について 中央環境審議会中間答申 |
|
| 1998年10月 | 「地球温暖化対策の推進に関する法律」制定 | |
| 1998年11月 | COP4(ブェノスアイレス) | 地球温暖化防止キャンペーンロゴマーク決定 |
| 1998年12月 | 地球温暖化防止月間の実施(1〜31日) | |
| 1999年4月 | 地球温暖化対策推進法の施行期日を定める政令公布 「地球温暖化対策に関する基本方針」閣議決定 |
|
| 1999年7月 | 全国地球温暖化防止活動推進センターを指定 「財団法人 日本環境協会」 |
|
| 1999年10月 | COP5(ボン) |
国内においても、1970年代の早い時期から環境庁や気象庁等の関係省庁において地球温暖化問題に関する検討が進められてきました。一方、地球環境問題が国際的な重要な課題になるにつれて政府一体となって総合的に施策を進めていく必要が生じ、1989年5月に「地球環境保全に関する関係閣僚会議」が設置され、また、同年7月には環境庁長官が地球環境問題担当大臣に任命されるなど、国内体制の整備も進んできました。
このような経緯を経て1990年10月に「地球温暖化防止行動計画」が策定されました。「地球温暖化防止行動計画」は、温暖化対策を計画的・総合的に推進していくための政府として方針と今後取り組んでいくべき可能な対策の全体像を明確にしたものです。この行動計画においては、二酸化炭素の排出抑制の目標について
|
一人当たりの排出量: 総 排 出 量 : |
2000年以降おおむね1990年レベルで安定化を図る 革新的技術開発等が早期に大幅に進展することにより、2000年以降 概ね1990年レベルで安定化するように努める |
|---|
としています。このために、都市・地域構造、交通体系から一人ひとりのライフスタイルにわたる広範な対策を掲げています。
また、二酸化炭素以外の温室効果ガスの排出抑制、二酸化炭素吸収源である緑の保全や様々な技術開発などの対策の推進も含まれています。
◆地球温暖化対策の推進に関する法律」(地球温暖化対策推進法)
地球温暖化対策推進法は、1998年10月9日に公布されました。1997年のCOP3での京都議定書の採択を受け、国、地方公共団体、事業者、国民が一体となって地球温暖化対策に取組むための枠組みを定めたものです。
・国、地方自治体、事業者、国民の全ての役割を明らかにします。
・6つの温室効果ガスの全てを対象にした取り組みを促進します。
・国、地方自治体はもちろん、相当量を排出する事業者についても、計画づくりやその実施状況の公表を促します。
・全国的な取り組みでなく、地方の実情に応じたきめ細かな対策を促進します。
・地球温暖化防止活動推進委員や地球温暖化防止活動推進センターといった仕組みを設けます。
1.地球温暖化対策に関する基本方針 (環境白書より)
地球温暖化対策推進法に基づき、政府では、地球温暖化対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、「地球温暖化対策に関する基本方針」を定めています。
基本方針においては、
a.地球温暖化対策の推進に関する基本的方向
b.国、地方公共団体、事業者及び国民のそれぞれが講ずべき温室効果ガスの排出の抑制等のための措置に関する基本的事項
c.政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のための実行措置について定める計画(実行計画)に関する事項
d.温室効果ガスの総排出量が相当程度多い事業者について温室効果ガスの排出の抑制等のための措置(他の者の温室効果ガスの排出抑制等に寄与するための措置を含む)
に関し策定及び公表に努めるべき計画に関する基本的事項
について定めることにしています。
2.全国地球温暖化防止活動推進センター
地球温暖化対策推進法の施行に伴い、 全国地球温暖化防止活動推進センターとして(財)日本環境協会が指定されました。同センターでは、地球温暖化防止に関する情報提供拠点としての機能やNGO・各自治体が実施する活動の支援拠点としての役割を担っています。また、各都道府県にも都道府県地球温暖化防止活動推進センターが指定され、市民や自治体などが推進する実際の温暖化防止活動に、より密着した支援活動が展開されることとなりますが、これらの都道府県センターの立ち上げのための支援も実施することとしています。
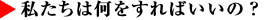
地球温暖化を防止するためには、温室効果ガスの排出の抑制、温室効果ガスの吸収源の保全・増進が必要となってきます。
各種の省エネルギー、代替エネルギーの利用等、現状の技術レベルでも温室効果ガスの排出を抑制するものは数多く存在します。その中で特に大きな効果が期待されるものとして、
しかし、技術的な対応だけで地球温暖化対策のすべてを担うことはできません。地球温暖化問題は私たちの大量生産・大量消費型の社会・文明そのものを見直す必要がある大きな課題です。従って、一人ひとりが環境保全型社会の構築に向けて、自らのライフスタイルを見直していくことが重要になってきています。例えば、自宅やオフィスにおいて、省エネ、リユース・リサイクルを心がけ、資源やエネルギーの無駄遣いをやめるなど、一つ一つの行動を見直していくことが大きな意味を持つようになってきています。