地球をとりまくオゾン層は、太陽光に含まれる有害な紫外線の大部分を吸収し、われわれ生物を守っています。
一方、代表的なフロンであるCFC(クロロフルオロカーボン)は冷媒、洗浄剤、発泡剤などに広く利用されてきましたが、いったん環境中に放出されると成層圏にまで達し、そこで強い紫外線を浴びて塩素を放出してオゾン層を破壊します。
その結果、地上に達する有害紫外線の照射量が増加し、皮膚がんの増加、生態系への悪影響などが生じるおそれがあります。
大切なオゾン層がCFCなどの人工の化学物質によって破壊されていることが明らかになっています。
そのメカニズムを簡単に示すと次のようになります。
オゾン層を破壊する物質としてはCFCの他に、ハロン、1,1,1-トリクロロエタン、四塩化炭素、HCFC(代替フロンの一種)、臭化メチルなどがあります。
地球規模でみた場合、熱帯域を除き長期的・全地球的にオゾン層の減少傾向が続いています。
特に顕著なのは南極上空のオゾン層の減少で、9月~10月頃にかけて南極上空のオゾン層が著しく減少する現象をオゾンホールと言い、1970年代の終わり頃から観測されるようになりました。また、このオゾンホールは近年大規模化が進んでいます。
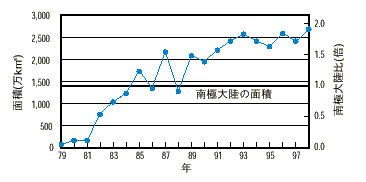 |
1985年に英国のファーマンらによって南極上空のオゾンホールについて報告されて以来、毎年9~11月頃に南極上空でオゾンホールが観測されており、特に1998年には、過去最大規模のオゾンホールが出現しています。 |
| オゾンホールの面積の経年変化 (気象庁 オゾン層観測報告1998) |
(注)オゾンホールの面積:オゾン全量が220m atm-cm以下の領域の面積 |
| 1979年10月 | 1998年10月 |
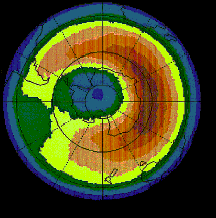 |
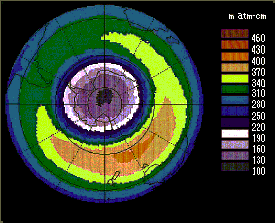 |
1979年10月、1998年10月の月平均オゾン全量の南半球分布
(気象庁提供データ)
| (注)m atm-cm:オゾン全量を表す単位。オゾン全量とは、大気の鉛直気柱に含まれるオゾン量をいい、300m atm-cm は、この気柱の中の全てのオゾンを0度(摂氏)・1気圧に圧縮したとき、3mmの厚さに相当する。 |
しかし、モントリオール議定書による規制の効果により、北半球中緯度付近においては、CFC-11,-12,-113の濃度の増加傾向の鈍化がみられます。
オゾン層が破壊されることにより地上に降り注ぐ紫外線が増加(特に波長の短い有害な紫外線ほど影響が大きい)します。このため、例えば私たちの生活や環境に対する以下のような悪影響の生じるおそれがあります。
オゾン層の保護に関しては、国際的な枠組みとして国連環境計画(UNEP)を中心として検討を重ね、1985年3月に「オゾン層の保護のためのウィーン条約」が採択されました。
そして1987年9月にはこのウィーン条約に基づいて具体的な規制を盛り込んだ「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」が採択されています。このモントリオール議定書によって5種類の特定フロンおよび3種類の特定ハロンの生産量の削減が合意されました。
その後、その他のオゾン破壊物質も規制物質として追加されて、それぞれ削減スケジュールが定められ、CFC等の生産を1996年までに全廃するなど規制物質の削減に努めています。
モントリオール議定書に基づく規制スケジュール(1997年9月改正)
各物質のグループ毎に、生産量及び次式で算定される消費量が削減されている。 わが国はウィーン条約及びモントリオール議定書に加入するとともに、これらの国際約束を的確かつ円滑に実施するため、1988年に「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」(オゾン層保護法)を制定しています。オゾン法保護法はモントリオール議定書の改正を受けて1991年と1994年及び1998年に改正を行っています。 ・議定書に基づきわが国が遵守すべき特定物質の生産量及び消費量の基準限度などオゾン層保護に関する基本的事項の公表 などの規定を設けています。 オゾン層保護法により、フロン使用事業者における排出の抑制や使用の合理化を義務づけていますが、一般市民に対する規制は定められていません。しかし、身の回りにもフロンを用いている生活用品はまだまだたくさん残っています。 また、 ・カーエアコンの冷媒の補充をガソリンスタンドや整備工場で頼む際に、不足分だけ補充するようにする など、ちょっとした行動や問題意識の持ち方により、フロンの排出を抑制できるだけでなく、事業者の意識改革にもつながります。さらに、地域で設置されているフロン回収等推進協議会などの活動に協力することにより、フロンの排出抑制に一層貢献する事もできます。
物 質 名
先進国に対する規則スケジュール
途上国に対する規則スケジュール
附属書A グループⅠ
1989
年以降
1986年比
100
%以下
1999
年以降
基準量比※7
100
%以下
(特定フロン)※1
1994
年
25
%以下
2005
年
50
%以下
1996
年
全廃
2007
年
15
%以下
2010
年
全廃
附属書A グループⅡ
1992
年以降
1986年比
100
%以下
2002
年以降
基準量比※7
100
%以下
(ハロン)※2
1994
年
全廃
2005
年
50
%以下
2010
年
全廃
附属書B グループⅠ
1993
年以降
1989年比
80
%以下
2003
年以降
基準量比※8
80
%以下
(その他のCFC)※3
1994
年
25
%以下
2007
年
15
%以下
1996
年
全廃
2010
年
全廃
附属書B グループⅡ
1995
年以降
1989年比
15
%以下
2005
年以降
基準量比※8
15
%以下
(四塩化炭素)
1996
年
全廃
2010
年
全廃
附属書B グループⅢ
1993
年以降
1989年比
100
%以下
2003
年以降
基準量比※8
100
%以下
(1.1.1-トリクロロエタン)
1994
年
50
%以下
2005
年
70
%以下
1996
年
全廃
2010
年
30
%以下
2015
年
全廃
附属書C グループⅠ
1996
年以降
基準量※6(キャップ2.8%)比
100
%以下
2016
年以降
2015年比
100
%以下
(HCFC)※4
2004
年
65
%以下
2040
年
全廃
2010
年
35
%以下
2015
年
10
%以下
2020
年
全廃
(既存機器への補充用を除く)
附属書C グループⅡ
1996
年以降
全廃
1996
年以降
全廃
(HBFC)
附属書E グループⅠ
1995
年以降
1991年比
100
%以下
2002
年以降
基準量比※9
100
%以下
(臭化メチル)※5
1999
年
75
%以下
2005
年
80
%以下
2001
年
50
%以下
2015
年
全廃
2003
年
30
%以下
(クルティカルユースを除く)
2005
年
全廃
(クリティカルユースを除く)
消費量=(生産量)+(輸入量)-(輸出量)
(※1)CFC-11,12,113,114,115
(※2)halonー1211,1301,2402
(※3)CFC-13,111,211,212,213,214,215,216,217
(※4)HCFC-21,22,31,121,122,123,124,131,132,133,141,142,151,221,222,223,224,225,226,231,232,233,234,235,241,242,243,244,251,252,253,261,262,271
なお、HCFCは消費量のみが規制される。
(※5)検疫及び出荷前処理用として使用される臭化メチルは、規制対象外となっている。
(※6)基準量は、次式で算定される。なお、次式中のx%をキャップと呼ぶ。
基準量=HCFCの1989年消費量算定値+CFCの1989年消費量算定値×(x%)
(※7)基準量は、1995年から1997年までの生産量・消費量の平均値または生産量・消費量が1人あたり0.3キログラムとなる値のいずれか低い値
(※8)基準量は、1998年から2000年までの生産量・消費量の平均値または生産量・消費量が1人当たり0.2キログラムとなる値のいずれか低い値
(※9)基準量は、1995年から1998年までの生産量・消費量の平均値
オゾン層保護法ではモントリオール議定書で規制の対象となっている物質を「特定物質」として、
・特定物質の製造数量などの規制
・特定物質の使用事業者による排出抑制・使用合理化の努力
・オゾン層および大気中の特定物質の濃度の状況の観測および監視
私たちは何をすればいいの?
特に、冷媒として使用されているフロンについては、機器を廃棄する際にフロンを大気中へ放出せずに回収し、分解処理(破壊)することが望ましく、そのために事業者や使用者等が応分の費用負担や協力をする必要があります。
・自動車を廃車にする際、解体に回す前にフロンを回収してもらう