 |
立川武蔵(国立民族学博物館教授)編著
A5判上製・308頁
|
| 現代ほど人々が癒しや救いを強く求めている時代もないだろう。だが、宗教的な癒しや救いは、他者から安易に与えられるものではない。厳しい修練を積んだ結果、身体で確かめるものである。宗教的実践の現状認識、アジアの宗教的伝統の歴史的概観をふまえて、癒しや救いに至るまでに必要な文化装置と修練の現実と可能性を問う。 |
| 主な目次 序章 癒しと救いを求めて(立川武蔵) 1 俗なるものの洪水 2 癒しと救い 3 救いと自己否定 4 今日の精神的状況 I 現代における癒しと救い 1章 日本近現代における〈癒しの技法〉-手かざし(浄霊)の誕生について(正木晃) 1 問題の所在 2 手かざし開発の歴史的前提 3 霊的技法の現況 2章 聖なる狂気-沖縄シャーマニズムにおける憑依現象(塩月亮子) 1 沖縄におけるシャーマンの憑依体験 2 憑依に対する弾圧史 3 ユタの〈ブリコラージュ的戦術〉 4 精神医学と憑依 5 〈神聖な狂気〉が生み出す癒しと救い 3章 〈他界〉の体験と時間の観念(蛭川立) 1 シャーマニズムと聖なるもの 2 死と再生の体験 3 近代と〈他界〉 4章 魂の危機と癒し(甲田烈) 1 魂の危機とは何か 2 ロベルト・アサジョーリの精神統合論 3 ケン・ウィルバーによる精神病理の発達論 4 スタニスラフ・グロフの魂の危機理論 5 クリシュナムルティの〈プロセス〉 6 魂の危機からの問い 5章 人間による救済-即身仏との対話(フィクション)をとおして(坂田昌彦) 1 澄門海上人 2 嵐のなかの対話 3 救済をめぐって 4 それぞれの道 II アジアの伝統における癒しと救い 6章 ヒンドゥイズムにおける救済(日野紹運) 1 インド思想の源流 2 シャンカラについて 3 バクティの影響 4 タントリズムの影響 7章 インド自然哲学における解脱(和田壽弘) 1 コンピュータとインド哲学 2 ヴァイシェーシカ学派の自然哲学 3 輪廻と解脱 4 解脱と生 8章 仏教における殺しと救い(森雅秀) 1 宗教は危険なのか 2 鬼子母神と大元帥明王 3 慈悲の力 9章 チベット人の葬儀(小野田俊蔵) 1 臨終からポワ(遷魂)の儀式まで 2 野辺送りの準備と湯灌 3 通夜と葬送 4 本 葬 5 忌明けから年忌法要 10章 親鸞思想における病・治療・健全(広田デニス) 1 親鸞の仏道 2 人間存在における「病」 3 治 療 4 人間存在の健全状態 III 宗教実践の可能性 11章 人は「自然」に還れるか(廣澤隆之) 1 「癒し」の実現としての救い 2 「自然」の概念をめぐって 3 仏教にみる「自然」 4 アニミスティック な自然観 12章 観想法という行法(佐久間留理子) 1 心と身体の蘇生 2 観想法の実際 3 観想法と憑霊 4 行者が手にしたもの 13章 あるネパール仏教僧の家族(山口しのぶ) 1 ラトナカジ氏一家との出会い 2 ラトナカジ家再訪 3 一九九四年-家族の新しい門出 4 カトマンドゥ、パタンの仏教僧たち 5 ラトナカジ家のガターン・ムガ 6 暗転-家長の死 7 救いの手だてとしての儀礼 14章 ネワール密教における身体の機能(吉崎一美) 1 ネワール密教の儀礼構造 2 壺の世界観 3 壺としての身体 4 壺としての身体はいかにして得られるか 5 霊媒師(ディオ・マージュ)考 終章 行為としての癒しと救い(立川武蔵) 1 変成という行為 2 負 債 3 心身症 4 聖なるもの あとがき |
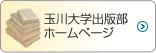 |