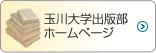| 序章 |
|
| 一 |
主題 |
| 二 |
方法
|
| 一章 |
四年制大学の一元化 |
| 一 |
『米国教育使節団報告書』と高等教育改革
| 1 |
|
『報告書』の意義 |
| 2 |
|
『報告書』の高度教育に関する勧告 |
| 3 |
|
第四委員会「スティーブンス文書」 |
| 4 |
|
師範学校の四年制化 |
|
| 二 |
日本側教育家委員会報告書と高等教育改革案
| 1 |
|
日本側教育家委員会 - 南原繁の役割 |
| 2 |
|
日本側教育家委員会報告書と高等教育改革案 |
| 3 |
|
日本側教育家委員会「報告書」の提出をめぐる謎 |
| 4 |
|
「戦後における学校制度案」 - CI&E教育課オアの検証 |
|
| 三 |
東京帝国大学教育制度研究委員会と高等教育改革案 |
| 四 |
教育刷新委員会 - 「旧制高等学校」存置をめぐる攻防 |
| 二章 |
大学基準協会と女子のリベラルアーツ・カレッジ |
| 一 |
CI&E教育課の高等教育改革政策 |
| 二 |
大学基準協会の設立をめぐる混迷
| 1 |
|
『米国教育使節団報告書』の示唆 |
| 2 |
|
CI&E教育課の混乱 |
| 3 |
|
チャータリングとアクレディテーションの混乱 |
| 4 |
|
チャータリングとアクレディテーションの分離と変容 |
| 5 |
|
大学評価 |
|
| 三 |
女子大学の誕生
| 1 |
|
CI&E教育課と文部省の攻防 |
| 2 |
|
女子リベラルアーツ・カレッジの模索 |
| 3 |
|
ホームズと神戸女学院 |
| 4 |
|
女子大学連盟の結成と役割 |
| 5 |
|
国立女子大学の設立 |
|
| 三章 |
米国人文科学顧問団の来日 - 人文科学研究の強化 |
| 一 |
人文科学研究の欠落 |
| 二 |
顧問団の成立経緯および報告書の作成
1
2
3
4
5 |
|
日本側からの人文科学者招聘の要請
団員の人選経緯
報告書の概要および執筆担当者 - 「マーティン文書」
米国人文科学顧問団日本側委員長南原繁の役割
日本側の影響を受けた最終『報告書』の内容 |
|
| 三 |
『報告書』の影響
1
2
3
4 |
|
人文科学研究の強化
『日本国憲法』第八九条および第二三条との矛盾の解消
図書館の強化
人文科学研究のための啓発活動 |
|
| 四 |
顧問団の影響力 |
| 四章 |
アメリカの大学におけるゼネラル・エデュケーション改革の動向 |
| 一 |
「ゼネラル・エデュケーション」の歴史的動向 |
| 二 |
シカゴ大学におけるゼネラル・エディケーションの理念と実践
1
2
3
4
5
6
7 |
|
歴史的および社会的背景
創設者ハーパーの理念と実践
改革者ハッチンスの理念と実践
ハッチンスの大学改革論「大学を救う道」
カリキュラム編成の特徴 - 一九四〇〜四一年版『シカゴ大学学報』
大実験の挫折と新たな挑戦
日本の高等教育改革との関連 |
|
| 三 |
ハーバード委員会報告書『自由社会におけるゼネラル・エデュケーション』
1
2
3 |
|
歴史的および社会的背景
大学基準との関連
ゼネラル・エデュケーションと社会科との関連 |
|
| 四 |
ゼネラル・エデュケーションの実践 - ハーバード・カレッジの場合 |
| 五章 |
「一般教育」の混迷一理念の欠落 |
| 一 |
混迷の源泉
1
2
3
4
5
6
7
|
|
“General Education”の由来
「一般教育」か「一般教養」か
『米国教育使節団報告書』 - リベラルアーツ・カレッジの模索
『報告書』と上原専祿
日本側教育家委員会報告書 - 「一般教育」理念の欠落
旧制高等学校 - 「高等普通教育」の限界
旧制大学に対する批判 |
|
| 二 |
一般教養科目の導入過程
1
2
3
4
5
6
7 |
|
大学基準協会と教育刷新委員会
大学基準協会と一般教養科目
大学基準の改訂
ゼネラル・エデュケーションとマグレール
「一般教育」と「専門教育」
一般教養科目の配置方法
大学設置基準の制定 |
|
| 三 |
米国対日工業教育顧問団 - 人文・社会科学の二系列カリキュラムの提言
1
2
3 |
|
顧問団の来日
『報告書』と「ゼネラル・エデュケーション」に関するカリキュラム
和田小六の一般教育論―東京工業大学における教育改革 |
|
| 四 |
韓国における高等教育改革とゼネラル・エデュケーションの意義 |
| 五 |
ドイツにおける高等教育改革とゼネラル・エデュケーションの意義 |
| 六 |
「一般教育」の混迷の原因 |
| 六章 |
単位制の形骸化-「自学自修」の精神の欠乏 |
| 一 |
単位制の誤解 |
| 二 |
単位制の導入過程
1
2
3 |
|
単位制の起源
大学基準協会と大学基準
ウィグルスワースの「新制大学の概念」 |
|
| 三 |
大学設置基準の制定と単位制 |
| 四 |
大学設置基準の大綱化と単位制 |
| 五 |
単位制の形骸化の原因 |
| 七章 |
短期大学の成立経緯 - 「旧制高等学校」の温存の阻止 |
| 一 |
発足期の混乱 |
| 二 |
米国教育使節団と「ジュニア・カレッジ」論
|
| 三 |
教育刷新委員会における短期大学論議
1
2 |
|
教育刷新委員会における論議
「トレーナー文書」のなかの「ジュニア・カレッジ」論 |
|
| 四 |
占領軍当局の動向
1
2
3
4 |
|
教育刷新委員会連絡委員会の記録
トレーナーの『回顧録』
GHQにおける「ジュニア・カレッジ」論議
イールズと「ジュニア・カレッジ」論争 |
|
| 五 |
河井道と短期大学
1
2 |
|
日本側教育委員会委員 - 女性委員の人選
河井道と短期大学 |
|
| 六 |
『学校教育法』と短期大学設置基準
1
2
3
4 |
|
『学校教育法』の一部改正
短期大学「恒久化」の論議
短期大学設置基準
短期大学設置基準の大綱化 |
|
| 七 |
短期大学の活路 - コミュニティ・カレッジとしての役割 |
| 八章 |
大学院改革の挫折 - 「論文博士」の温存をめぐる攻防 |
| 一 |
論文博士の存続をめぐる混乱 |
| 二 |
占領下の高等教育改革政策における大学院改革
1
2 |
|
日本側教育家委員会と南原繁
大学院教育に対する米国学術顧問団の批判 |
|
| 三 |
教育審議会および教育刷新委員会における大学院論議
1
2 |
|
教育審議会における大学院論議
教育刷新委員会における大学院論議 |
|
| 四 |
CI&E教育課の内面指導 - 大学基準協会における大学院論議
1
2
3 |
|
大学基準協会への内面指導―「基準委員会議事抄録」
大学院基準の起案
学位に関する事項の決議 |
|
| 五 |
論文博士に対するCI&E教育課と日本側との攻防
1
2
3 |
|
大学設置審議会第八特別委員会小委員会からの要請
大学設置審議会第八特別委員会への回答
課程制大学院改革の不徹底 - CI&E教育課高等教育班内部の葛藤 |
|
| 六 |
韓国における論文博士の改革 - 旧制への決別 |
| 七 |
新制大学院の使命 - 自立した研究者養成のための課程制大学院 |
| 結章 |
|
| 一 |
本書の概要 |
| 二 |
「挫折」の原因 |
| 三 |
課題と展望
1
2
3
4
5 |
|
「二一世紀高等教育」のプロローグ
「一般教育」と「単位制」の再構築
教授法の研究・開発 - FD活動の促進
二一世紀日本の高等教育と教養教育
将来展望 - 学士課程教育における優れた授業実践 |
|