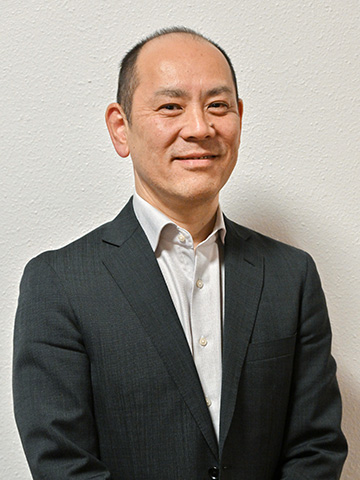髙城 宏行 教授TAKAGI Hiroyuki
Q & A
- 担当授業は?
- 異文化間コミュニケーション、多文化社会論、Study Abroad Seminar A、Study Abroad Seminar B、グローバル・シティズンシップ、キャリア・マネジメント論、海外留学入門
研究紹介
高等教育の国際化戦略に関する国際比較

グローバル化に対応する高等教育機関の国際化のアプローチを「競争型」(実用的理念、国家的立場など)と「協力型」(価値的理念、国際的立場など)に分類し、さらに教育方針を「プロダクト型」(認知的目標、教育内容重視など)と「プロセス型」(情意的目標、学修経験重視など)に分け、それらを組み合わせた4つの類型(①競争-プロダクト型、②競争-プロセス型、③協力-プロダクト型、④協力-プロセス型)を用いて、日本と欧米をはじめ諸外国と比較しながら動向を考察しています。
グローバル化の進展で国際競争が激化する中、欧米と同様に日本も①競争-プロダクト型(グローバル経済において国際競争力を持つ人材に必要な専門知識やスキルを教員主導で修得させるモデル)へのシフトが見られましたが、一方で複雑化するグローバル課題に対応する④協力-プロセス型(内発的に動機づけられた学習者中心の国際交流・経験を通しグローバル社会の一員となるための異文化コンピテンスの修得を助長するモデル)が近年重視されています。しかし、国や教育機関はそれぞれの文脈に適した国際化戦略を立てており、不確実性、可変性の高いグローバル化のプロセスにおいて、類型の収束と分散の両面が見られています。
K-16/K-20教育連携による国際教育カリキュラムの開発
世界的に競争と共生が進むグローバル社会において、日本の成長を牽引するグローバル人材の育成が推進されています。日本では多くの大学にて海外留学プログラムや英語開講科目の充実等、カリキュラムの国際化を進めていますが、英語力または経済的な問題、内向きな日本人学生の特性等により留学者数は低迷し、また日本人学生の英語力不足や受動的な学修態度により、学内における国際交流・共修は未だ限定的な状況にあります。
グローバル人材とは、単に英語を使い世界で活躍する職業人のことではなく、グローバル社会において広い視野を持ち多様な文化・社会的背景を持つ人々と共生・協働し世界的な課題に取り組む市民を意味します。よって、グローバル社会における人材育成は、国際志向や外国語能力のある一部の学生だけでなく、全学生を対象に全学的に取り組むだけでなく、大学入学以前から外国語学習や異文化経験を通し、留学や国際的な学修への動機づけを行うために、初等・中等教育段階を含めたK-16、さらには大学院、社会人教育を含めたK-20の視点が必要です。K-16/K-20異校種間連携による国際教育の推進および、カリキュラム開発の可能性と課題について国内外の先進的な事例を参考に研究をしています。
グローバルコンピテンスの育成における学修経験の効果測定
グローバル人材またはグローバル市民に必要な資質・能力として、異文化理解、コミュニケーション能力、異文化適応力、チャレンジ精神等を包括するグローバルコンピテンスの育成が重要とされています。OECD(経済協力開発機構)は国際的な生徒の学習到達度調査(PISA)の新たな尺度にグローバルコンピテンスを加え、その能力を 1)地域的、世界的、そして異文化間の問題を検討する能力、2)他者の視点と世界観を理解し認める能力、3)異なる文化を持つ人々とオープンで適切で効果的な関わりを持つ能力、4)共同体の幸福と持続可能な開発のために行動する能力の4つにまとめています。
これらの能力を、生徒・学生はどのような経験を通して習得・向上しているのか、学習者の特性や経験によりどのような有意差があるか、学習者の特性に応じた学習機会や学修目標をどのように設定すべきかなどの研究の問いを立て、量的調査(学習・成長・変化のプロセスや成果を測定するツール「Beliefs, Events, and Values Inventory (BEVI)」を使用)と質的調査(学習者へのインタビューや課題のテキスト分析など)を行なっています。
グローカル・イノベーターの人材開発
ウィズ・ポストコロナにおける生活様式の変化(テレワークによる地方への移住、ノマドワーカーの増加、国内および海外から日本への新たなモビリティなど)を日本の地域創生に繋げようとする動きが活発化しています。産官学協働により地方と都市そして世界を繋ぎ、多様な人々と協働して新たな価値やサービスを創造し、地域社会や産業を振興・復興・創生し持続的な発展に寄与する人材(仮称:グローカル・イノベーター)の開発について研究を始めています。
海外留学に関する研究
・海外留学に対する学生の意識調査
・オンラインによる国際プログラム・国際交流(COILなど)の学修成果に関する調査
・海外大学とのダブル・ジョントディグリープログラムの質保証に関する調査
ゼミガイド
グローバル社会で求められる資質・能力の修得および育成について考えます
- グローバル人材
- 市民の育成
- 教育の国際化
グローバルまたはグローカルに活動する人材・市民、もしくはそれらを育成する教育者を目指し実践的な学びを行います
- グローバル化の進展や科学技術の発展により変化の激しい不確かな時代において、社会や経済界で求められるグローバル人材または21世紀型市民とはどのような資質・能力を備えた人々なのか、またそのような人材を育成するためにはどのような教育・学習が必要なのかについて考え、自らもそれらの資質・能力の修得を目指します。
教室内外での主体的な研究および実務者との交流やフィールドワークなど実践的な学びを行います

学生それぞれの関心や問題意識に基づいたテーマを設定し研究を進めていきます。教室内での研究発表や意見交換の他、テーマに関係する国内外の機関や企業(例えば在東京の外国公館・国際機関やグローバル企業等)の担当者や大学関係者を訪問または本学に招き直接対話をして意見交換を行うなど実践的な学びを行います。
PICK UP
グローバル人材・市民・ティーチャーとして世界を舞台に活動しよう!

多様な国際的な学修経験を積み、グローバル人材・市民・ティーチャーの素養を身に付けましょう。ゼミ生の希望に応じ、海外の大学生との国際共修(オンラインを含む)や国内外でのゼミ合宿の実施を検討します。