丹治 めぐみ 教授TANJI Megumi

Q & A
- 専門分野は?
- アメリカ文学・文化研究
- 主な著書・論文は?
- 著書・訳書
- 『聖書からの贈り物』(編書、2025)
- 『ナザレの人イエス』 (翻訳、2014)
- 『知っておきたいアメリカ文学』 (共著、2010)
- 『祈りの美術館』 (翻訳、2005)
- 『現代アメリカ大学生群像』 (翻訳、2000)
- “Family Lives in the Pandemic Year ―A Study of Anne Tyler’s French Braid and Elizabeth Strout’s Lucy by the Sea―” (論文、2024)
- 「英語教員養成課程における文学教材の扱い―Alice Walker "The Flowers" 精読演習の試み―」(論文、2023)
- 最近関心のある研究・教育分野は?
- 多文化共生を図ってきたアメリカ文化の在り方。マーク・トウェインの小説作品や、女性作家が文学作品でどのように自己を表現してきたかに関心を持ち続けています。
- 担当授業は?
- Basic Academic English Skills A、Basic Academic English Skills B、Study Abroad Seminar A、Study Abroad Seminar B、英語圏の言語と文化、英語文学、英語文学購読
研究紹介
アメリカ文学の世界へ
英語英米文学を専門とする学科で学んだ大学時代、何を専攻するかを意識する時期がきました。イギリス文学か?アメリカ文学か?それとも、英語という言語そのものを研究対象とする英語学か?
辞書をひいて英語を読むこと、そして物語を読むことが好きだったので、自然に文学を学びたいという思いをもち、さらにいくつかのきっかけがあってアメリカに関心を向けました。学生時代に抱いた問題意識は、その後の研究に続いています。
ひとつは、話しことばの文学の伝統。19世紀アメリカの作家マーク・トウェインは、代表作『ハックルベリー・フィンの冒険』で主人公の少年にふつうの日常生活のことばで語らせました。知識も教養もないので、文法的なまちがいがあるし、気のきいた慣用句などは使えません。その分、自分の見たまま、感じたままを、自分にしかできない表現で語るこの作品を大学の授業で知り、すぐに読みたい!と思って原書を入手しました。ところが、あっさり挫折。整った英語しか読んだことがなかったためか、歯がたちませんでした。でも、アメリカ的な題材をアメリカ的な言語で語る作品に出合ったことで、アメリカ文学をもっと知りたいと思うようになりました。
もうひとつは、文学作品にみられる、さまざまな女性のイメージ。職業を持ちながら家庭生活もできるだろうか、ということをずっと考えていた学生時代、19世紀以降のアメリカ女性作家たちが書いた多くの作品が注目されるようになっていて、同じような問いと悩みが描かれていることを知りました。自分にとって最も身近で切実な問題に、100年以上前の、異なる文化に生きていた多くの女性がぶつかっていた!どうやって壁を越えたり、越えられなかったりしたのかを作品から読み取ることに、夢中になりました。
「地域研究」の視点
Area studiesは、ある地域の歴史・文化・社会制度などを学際的に(学問の領域を超えるようにして)とらえ、その地域の個性を明らかにしようとするものです。
アメリカ文学について考えるときに、このような「地域研究」の視点をもつことが助けになります。歴史と文化的伝統の長さでは、アメリカはヨーロッパにかないません。しかし、17世紀から始まったヨーロッパ人による植民地建設、18世紀に達成した独立、19世紀に国土も人口も増大、と変化していくにつれて、ヨーロッパとは異なるアメリカの文化・文芸を作り出そうとする機運が高まっていきました。「英米」とか「欧米」といったくくり方をしますが、アメリカの文化や文学の「アメリカらしさ」とはいったい何だろう?という問いが生まれます。作品を読みながら、常にこの問いを念頭に置いています。
アメリカは、直接・間接に私たちが生きる社会や文化に影響を及ぼす存在です。近年は、分裂と格差の拡大という観点からアメリカを見ることが多い傾向にありますが、それも含めて、いったい何がアメリカをアメリカらしくしているのかを考えることは、自分が生きる社会や文化の現在とこれからについて考えることにつながります。
研究対象の作家 Anne Tyler
アン・タイラー(1941~)はその作品がさまざまな言語に翻訳されており、日本語でも10作以上が出版されている、現代アメリカを代表する作家の一人です。第1作の発表が1964年、最新作は2025年。この間一貫して、家族の関係のなかに人物を置いていることが特徴です。タイラーの作品は、特定の時代や地域を超えて、家族というものがもつ普遍性を意識させます。だからこそ、多くの国で読者を得ているのでしょう。
タイラー作品はその時代のアメリカ社会を描いていないとして、批判を受けることがあります。人は社会と無関係に存在することはありません。タイラーは本当に社会を描いていないのか、描いているとしたらどのような描き方になっているのか。このような視点も持ちながら、作品研究に取り組んでいます。
文学探究の面白さ
なぜ小説を書くのか、という問いに対して、アン・タイラーは”I write because I want more than one life.”と答えました。文学作品の書き手だけでなく、読み手についても同じことが言えるのではないでしょうか。まさに、文学の世界を探究する面白さを言い表したことばだと思います。
もちろん、研究には冷静な批判的態度が必要です。でも、根底に「面白い、もっと読みたい」という気持ち、あるいはmore than one lifeを求める好奇心があって、それが原動力になることも確かです。
文学探究の面白さをどのように英語教育に結びつけていけるか、ということも、今後の研究課題と考えています。
ゼミガイド
アメリカ文化の「アメリカらしさ」を考える
- アメリカ文化
- アメリカ社会
アメリカ文化の独自性と普遍的な広がり、私たち自身の生活や文化とのかかわりを考えます。
- アメリカの社会と文化を研究するということは、他の国や文化にない特徴を明らかにすること。最大の特徴は、国家としての歴史の短さと、国土の広さ、そして多民族・多文化であるという点です。その特徴が生み出した文化の独自性を探り、日本社会に生きる私たちがそこから何を得られるかを探究します。
地道に読む・調べる・表現する。

他国の文化を知るには、その国の歴史を知ることが必要。歴史学のゼミではありませんが、ヨーロッパ人による植民地建設の経緯から始めて、アメリカ史の全体像を何とかしてつかみたい。文献を読み、調べ、プレゼンを繰り返します。
PICK UP
コスモス祭文学部展では、テーマを決めて、ゼミで研究していることを展示発表します。
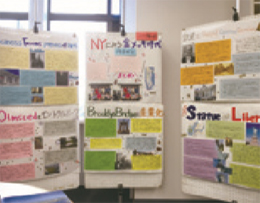
自分たちでテーマを決めるところから、作業が始まります。うまく協力できると、お互いのことをよりよく知る機会になり、充実した時間をすごすことができます。
