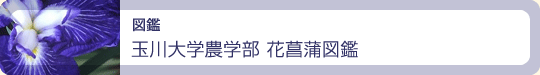TOP > 花菖蒲図鑑 > 品種一覧-あ行 > イマキュリート グリッター
いまきゅりーと ぐりったー
イマキュリート グリッター
Immaculate glitter
| アメリカ(例外) | 【花容】やや垂れた平咲き 【英数】六英 【花色】濃紫 【開花時期】6月中旬 (2021年6月27日、2022年は6月17日開花) |
| 分類 | : | アメリカ人のW.A.ペーン氏が育成したので、分類上は「アメリカ(例外)」。花被片の先端部がやや垂れる平咲きの六英花です。 |
|---|---|---|
| 花被 | : | 花径は15cmを超える大輪です。形状は大きい被覆変は円形で(8×8cm)、小さい方は楕円形(6×5cm)です。花被片は周縁部がやや波を打ったようになります。花被片の質は比較的厚く、基調色は鮮やかな紫色です。非常に良く目立つ白色の糸覆輪(白い縁取りがある)のある六英咲きです。 アイの周辺部は青紫色で、アイの先端部からは青紫色の筋が見えます。また、アイの黄色部分を起点にして周縁部に向かって紫色の細い筋が入ります。 |
| 花柱枝 | : | 花被片はやや斜め上に直立し、花色は花被片と同じ紫色で、中心部はやや薄い紫色、先端部は2裂開してずい弁が発達します。先端部は2裂開し、ずい弁が立ち上がります。ずい弁の先端部は円滑です。花柱枝やずい弁にも白色の細い糸覆輪が入ります。 |
| 備考 | : | 花被片の縁取りが白色の、花色がいわゆる「白覆輪」の品種はいくつかありますが、この品種は代表的なものの一つです。花径は20cm以上、花茎長は80cmです。1925年頃(大正14年頃)、アメリカ人のウイリアム・A・ペーン(William A. Payne)氏が育成した品種です。わが国からアメリカには1898年に横浜植木株式会社のニューヨーク支店を通じて輸出されました。これらの品種の中から、アメリカ人の手によって育成された品種があります。ウイリアム・A・ペーン氏はこのようにして日本から輸入した花菖蒲を用いて170品種近くを育成しました。 品種の育成当時は戦時中であったため、アメリカでは「パールハーバーアイリス」などと称されて品種の多くは紛失したようですが、現在はグローバル化の基、アメリカ人の目を通して見て育成したわが国の花菖蒲品種はこのように育成される、という重要なヒントになると考えて、本学では大切に栽培・保存しています(→花の品種改良の日本史)。 アメリカ系の品種は概して草丈が高く(70cm以上)、花径が大きくて(20cm程度)原色の濃いものが多いのが特徴です。このように花器官が大きく、花色も原色を強調するような品種は、日本人のイメージする花菖蒲の「淡い微妙な色合い」とは大きく異なるので、なかなか受け入れられないようです。 花菖蒲の図鑑には、アメリカ人が育成した品種はほとんど掲載されてなく、販売も限られています。本品種を栽培している花菖蒲園はほとんどありません。アメリカ人をはじめとした品種名は、花菖蒲園では「カタカナ名」で名札を立てて栽植されていますので、注意して見てください。 ウイリアム・A・ペーン氏の育成品種として有名な銘品種と呼ばれているものは、「イマキュリート グリッター」の他に、ザ・グレートモガールなどがあります。写真の一番最後のものには、右側に「ザ・グレートモガール」を一緒に写しました。 花菖蒲品種の分類は、江戸時代に育成した地域によって、江戸系、伊勢系、肥後系に分けていますが、このようにアメリカ人が育成した品種は、敢えて「アメリカ(例外)」と称することとしました。 本学では、このように来歴がはっきりしている歴史のある品種を収集して価値ある文化財的な品種として保存しています。本学のある町田市では、アメリカ人育成の品種は、開花した翌年には株の性質が弱くなる傾向があり、また、近年の温暖化により気温、水温が高くなるので丹精を込めて栽培しないと翌年の開花が難しく、なかなか増殖しない品種が多いようで、開花しても花茎が細くなり花径も小さく倒伏しやすくなります。開花翌年は株を充実させるために、敢えて花蕾を除去することもあります。 株自体は昨今の猛暑にも耐えうるのですが、毎年、開花させようとする場合には注意が必要です。 なお、学術的には白色の覆輪を持つ形質は非常に重要です。これまでに白色の覆輪を保有する野生のノハナショウブは発見されなかったのですが、本学の調査によって青森県の白神山地で明確な白色の糸覆輪を持つ個体が発見されました。この個体の花器官は、細胞構造に独特の特徴が見られます。花色は遺伝的に顕性(以前の優性)であることなど、多くの新知見が得られ、英文にて発表されています(Chino,N., T.Kobayashi and T.Tabuchi.. 2020)。 |
| 参考文献 | : |
|