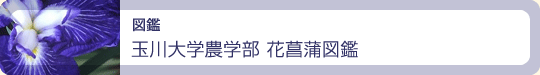たつたがわ
立田川
Tatsutagawa
| 江戸系 | 【英数】三英 【花色】白地 周縁部は濃紅覆輪 【開花時期】6月中旬から下旬 2022年は6月23日開花 2024年は6月20日開花 |
| 分類 | : | 江戸系の「古花」です。平咲きで先端部がやや下垂する三英花です。 |
|---|---|---|
| 外花被 | : | 形状は円形で(6×6cm)、平咲きです。肩の部分が波打ち、先端部にいくにつれて皺が見られることがあります。 花色は薄い紅紫色に白色の筋が入ります。基部は白色。遠目に見ると、基部は白色、周辺部には赤紫色の覆輪があります。 |
| 内花被 | : | 剣状で軸方向に立ち上がり先端部が尖ります。やや内巻きとなって周縁部は赤紫色、中心部は白色です。外花被片が非常に大きく目立ちますが、内花被片は小さく見えます。 |
| 花柱枝 | : | 白色地で周縁部に赤紫色のごく細い覆輪があります。先端部は2裂開して爪状のずい弁が発達します。ずい弁は先端部のみ紅紫色で、周縁部に細かい鋸歯が発達します。 |
| 備考 | : | 別名で「竜田川」と称することもあります。花径は15cm、花茎長は40cmで、花茎が細く折れやすい品種です。栽培は難しい部類に入ります。本学でも開花させるか、株を大きくするか毎年迷う品種の一つです。 江戸時代末期の1856年以前(安政2年)に松平左金吾(菖翁)によって育成された「菖翁花」であると言われていました。 『花菖蒲花銘』の図譜では、外花被片の周縁部の紅紫色の幅が広く、明瞭に描かれています。また、『花菖蒲大図譜』(栗林元二郎・平尾秀一、1971)にも、同様に外花被片のほとんどを紅紫色の覆輪が占める写真が掲載され、基部が白色です。 この点については、菖翁が育成した品種とは別品種であるという説と、菖翁が育成したが株分けによって年月が経過につれて紅紫色の部分が淡くなっていったとする説があります(平尾、1981年)。 また、菖翁が育成した品種は、そのまま肥後へと譲り受けられたので、肥後系古花の育成に大きく貢献していると言われています。肥後系古花の多くは6英ですが、3英花も存在し、その中に「立田川」に酷似する品種(「深芳野」)が存在します。 現存する「立田川(竜田川)」と呼ばれる株は、菖翁が育成した菖翁花かどうかが問題になります。 この点につき、菖翁花の起源であるノハナショウブ(自生地は信州・霧ヶ峰周辺と日光周辺)であるかを根拠にして、本学で分子生物学的に調べた結果、現存する「立田川」は、信州・霧ヶ峰付近や日光に自生する野生のノハナショウブと一致することがわかりました。よって、菖翁花であることが明らかになりました(Kobayashi and Tabuchi, 2024)。 江戸時代に育成された品種は、古文書による記述とは花の形状や花色、名称の漢字において、現存する株とは異なることが非常に多く存在します。 本品種の場合は「竜田川」となっています。それゆえ、古文書だけに頼らない、分子生物学的な知見によって判別していますが、根拠となるのは由来となった野生のノハナショウブと一致するかで行っています。 この点につき、昭和に入って花菖蒲品種を多数育成した育種家の平尾秀一氏(1981)は、その著書の中で科学的な知見の必要性も述べています。 「古文書の不確実な記述から想像をめぐらすにとどまっていては研究の進歩は望めないから、昔から今日まで伝わっている生き証人の花自体にもっと目をむけたいものです」。 本学では、科学的な知見を主とした紹介をしていますが、得られた知見と古文書の内容が合致すればより真実に近づくことになります。その点では、野生種のうち、信州のノハナショウブを用いて、菖翁花が育成された記載と、現存する株が一致した例は非常に大きな根拠資料になっています。 紅紫色の覆輪の幅の広さが減少する点については、本学で30年間にわたり、現存する「立田川」の同じ株を栽培すると、紅紫色の覆輪の幅に年次変化があることが明らかになりました。 このように、花色が古文書と異なる品種は、「霓裳羽衣(げいしょううい)」にも認められますので、現存する株の維持と保存、およびその調査が必要となります。 肥後系古花の育成に、「立田川」が大いに関与したとする説が有力です。この点について分子生物学的な研究を行った結果、肥後系古花の品種育成に貢献した品種に、現在の株の「立田川」が含まれ、その寄与率は78.4~100%でした。 現在の科学的な知見から得られたことは、以下に集約することができます。 ①現存する「立田川」の株は、分子生物学的な観点から、他の菖翁花の由来の根拠である信州・霧ヶ峰と日光のノハナショウブとは一致したので菖翁花である。 ②外花被片の紅紫色の覆輪の幅は年次変動があるので、品種の特性にはならない。 ③分子生物学的な観点から、肥後古花への育成の寄与率は78.4%であった。よって、現存する「立田川」は、肥後古花の育成に関与していた。 ④菖翁が当時の肥後に贈った「立田川」は、現存する「立田川」と同じである(ただし、「竜田川」の品種名であるかは不明)。 |
| 文献 | : |
|