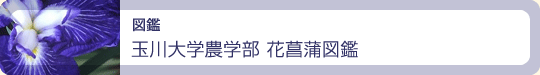げっきゅうでん
月宮殿
Gekkyu-den
| 伊勢系 | 【英数】三英 【花色】白色で薄い青色のぼかしが入ります 花径は15cm(2021年6月9日) 【開花時期】 2021年は6月9日に開花 |
| 分類 | : | 外花被片は丸弁で中心部から先端が下垂する三英花で、伊勢系の花菖蒲の「古花」に分類される歴史のある品種です。垂れ方の分類は→「不知火」を参照ください。 |
|---|---|---|
| 外花被 | : | 丸弁、円形で大きく発達し、花被片中心部から軸方向下方に下垂して垂れ咲きになります。花被片のうねり(波打ち)の程度は伊勢系の他の品種に比べるとやや少なく、花被片の向軸面(表面)に見られる縮緬状の構造を形成する細胞は周縁部にわずかに見られます。 花色は白色の地にわずかに藤色となります。もしくは青紫色の砂子、あるいはぼかしが入りますが、その程度には個体差があります。 |
| 内花被 | : | 形状は楕円形で幅が広く、軸方向にまっすぐ直立し、若干内巻きになります。花色は白色で、周縁部には明瞭な藤紫色の糸覆輪が発達します。しばしば、内花被片の白色部分に藤青紫色の斑紋が入る場合があります。写真の7枚目では藤青色の斑点が発達しています。 |
| 花柱枝 | : | 軸方向に斜め上に向かってまっすぐに伸長し、細長いのでアイの部分を隠すようになります。先端部は裂開してさじ状のずい弁が発達します。 ずい弁はやや上向き、あるいはやや内側に巻く構造となります。先端部は円滑で、鋸歯(くも手)は発達しません。花柱枝の色は、ややクリーム色を帯びた白色で、ずい弁も白色ですが背軸面(裏側)は、やや薄い藤青色です(個体差があります)。 |
| 備考 | : | 1940年以前に伊勢地方で育成された、いわゆる「伊勢古花」で、別名を「藤葉衣」と呼びます。本品種は一般には見かけることの少ない品種ですが、白色の三英花で、内花被片の周縁部には非常に明瞭な藤青色の覆輪が形成されるので、比較的区別しやすいです。
一般にハナショウブの染色体数は2n=24ですが、伊勢系の品種群の中には2n=25の品種があり、「月宮殿」もその一つと言われていました。本学の研究により、「月宮殿」は、2n=25の異数体であることが明らかになりました。他の伊勢系古花や伊勢系の品種群の起源となった、三重県斎宮の野生のノハナショウブの株にも認められました。詳細は「落葉衣」を参照ください。 この異数体がどうしてできたのか、また1本が加わることによる機能については本学で継続して研究中です。 |
| 参考文献 | : | ・平松 渚・平松渚・中村泰基・田渕俊人.2009.日本伝統の園芸植物,ハナショウブの特性に関する研究(第4報)伊勢系ハナショウブの外花被片の「しわ」(縮緬状構造)は,花被の向軸,背軸面の細胞形態の違いと伸長のギャップによって生じる.園芸学研究8(別2)579. ・Toshihito Tabuchi,Azusa Komine, Takayuki Kobayashi. 2013.Histological structure of the ‘Crepe-like’structure of the outer perianth in the Ise type cultivar in the japanese irises. International Symposium on Diversifying Biological Resources.46-47. ・田淵俊人.2016.花の品種改良の日本史(柴田道夫編).伊勢ハナショウブの成立.悠書館,東京.p250−251. ・小林孝至・田淵俊人.2020.エステラーゼアイソザイム分析による伊勢系品種のハナショウブの起源.園芸学研究.19(別1):416. ・Tabuchi, T. and T.Kobayashi. 2024. Characteristics and apprication style of Japanese irises (Hana-syoubu) 2.Ise-group. WORZ Book. 99. International Society for Horticultural Science |