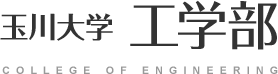第59回
1年生「チャイルドラボ 特別講義」
2025年7月15日、ソフトウェアサイエンスを学ぶ1年生を対象に、発達心理学と子ども向けコンテンツ開発の第一人者・沢井佳子(さわい よしこ)先生(チャイルド・ラボ所長/日本子ども成育協会理事)をお迎えし、特別講義「子どもの発達における”認知”の認知」を開催しました。本講義は人間が「わかる」とは何か——その原点である子どもの認知発達の視点から、AIやソフトウェア開発の未来を考える大変貴重な機会となりました。
講義では『ひらけ!ポンキッキ』の心理学スタッフ、ベネッセ『こどもちゃれんじ』や幼児教育番組『しまじろうのわお!』の監修、マクドナルド「ハッピーセット」のおもちゃ監修 等々、先生がこれまで実践されてきた“子どものための成育環境デザイン”の具体例をもとに、子どもの「遊び」や「学び」を支える環境づくりの工夫や社会的意義が語られました。さらに、ピアジェの認知発達理論がMITのAI研究やプログラミング言語「LOGO」「Scratch」の誕生に大きな影響を与えてきた歴史にふれ、「子どもの発達研究」と「AI研究」が根本で深く結びついていることを分かりやすくご解説いただきました。
また近年の研究を踏まえ、子どもの認知能力が胎児期から急速に発達していること、そして生後の発達の基盤となる「愛着形成」や「共同注意(大好きな人と一緒に世界を認識する経験)」の重要性が紹介されました。人間にとって、学びは単なる情報処理ではなく、他者との豊かなインタラクションや社会性に深く根差していることについて、具体例を挙げながらお話しいただきました。
講義後の質疑応答では、「空間認知能力はどうすれば鍛えられるか?」「コロナ禍でのマスク生活が子どもの顔認識に与えた影響は?」など、学生から多彩な質問が寄せられました。沢井先生はそれぞれの質問に豊富なご経験と研究成果をもとに丁寧にご回答くださり、技術と人間発達の関係についての理解がより深まりました。
今回の特別講義はソフトウェアサイエンスを学ぶ学生たちにとって、「人間の“わかる”を支えるAIとは何か?」「自分たちの開発する技術が人や社会の成長・発達にどう貢献できるのか?」を考えるきっかけとなりました。
最後に、ご多忙の中ご講演いただいた沢井佳子先生に、心より御礼申し上げます。


2025年8月14日 柴田健一講師