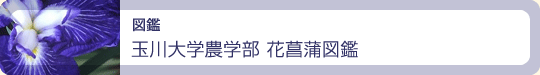うちゅう
宇宙
Uchu
| 江戸系 | 【花容】花被片が複雑に発達し、ねじれたような花容で、俗に「狂い咲き」と称しています 【英数】八重咲き(多弁) 【花色】紫青色に白色の筋、花被片の基部が白色 【開花時期】6月中旬(2021年は6月19日開花) |
| 分類 | : | 江戸系品種。花被片が多く、俗に「狂い咲き」と呼ばれている八重咲き(多弁)花です。 |
|---|---|---|
| 花被片 | : | 通常、花菖蒲の花器官の構造は、外側から花軸のある内側に向かって、外花被片、内花被片、花柱枝(雌しべに相当する部分)、雄ずいで構成され、それぞれ3枚ずつです。これらの花器官の全てが花被片化すると、花被片数が合計12枚になり、「宇宙」のような花容になります。 立体的な花容となり、園芸学的には「八重咲き」と称していますが、形態的には多弁花とした方が正しい表記かもしれません。本ホームページでは、花被片に見える部分の特徴を述べることにします。 一番外側の花被片と、その内側の花被片の花被片の形状は楕円形で、基本的に外側は大きく、内側に向かうにつれて小さくなります。花被片は厚く、大きく波打って「ひねったような状態」になります。周縁部にわずかな縮緬状構造が見られることがあります。 花色は、青紫色を基調として太い白筋が入ります。花被片の基部は白色で、最も奥の基部には黄色のアイが見えます。白色の筋は花被片の基部のアイ付近から放射状に周縁部に向かって発達しているように見えます。 なお、花被片の他に、次に述べる花柱枝や、花柱枝の裏側の雄ずいが花被片化して、しばしば軸方向に大きく立ち上がることもあります。この場合でも、その部分の花色は青紫色です。 生物学的には、花器官は種子を形成して子孫を残すために作られるものですが、雄しべや雌しべの部分も、花被片(花びら)になってしまうと、花粉や子房が作られないので、生物学的には種子は形成されません。 |
| 花柱枝 | : | 花器官の中央部に位置し、水平状ですが軸方向に向かって大きく立ち上がる場合があります。先端部が2裂開(個体によっては3~4裂開する場合もあります)し、先端部は花被片状のずい弁が形成されます。 花柱枝が軸方向に沿って裂開する個体も見受けられます。ずい弁の発達程度(大きさ)や形状には個体差があり、同じ花器官内で異なりますが、形状は小さな細長楕円の場合や、丸い個体などがあります。 周縁部は基本的には円滑ですが、「くも手」状に鋸歯が入る場合もあります。 ずい弁の先端部は花被片と同様に青紫色です。また、稀にとさか状の突起(クレスト)状構造が見られることがあります。 |
| 備考 | : | 江戸幕府の旗本、松平左金吾(本名)の作出した品種で、江戸系の花菖蒲の中では、最も歴史的な銘花の一つです。明治神宮では「おおぞら」と詠みます。花器官の形態から「連城の璧(れんじょうのたま)」から派生して育成されたのではないか、とも言われていました。 育成者の松平左金吾(自らを、「菖翁」と称したので以下、菖翁と記します)は、野生のノハナショウブを江戸の自宅に集め、園芸植物の花菖蒲を育成した最初の人物です。 その後、菖翁から花菖蒲の株を分譲された万年禄三郎や、小高伊左衛門を通して品種改良が行われたので花菖蒲は普及し、その後、江戸・堀切周辺(現在の葛飾区堀切一帯)に花菖蒲園が造成されました。これらの花菖蒲園では、さらに様々な品種群が育成、栽培されていきました。 『菖翁花』は平咲きではありません。菖翁自身の著した書物の中で、平咲きは好みではなく、「狂い咲き」や「奇花咲き」、花菖蒲であるとしています。 しかし、江戸・堀切一帯で『菖翁花』が育成され、その後、堀切を中心に花菖蒲園で観賞できるように育成されたので、現在では、育成地の江戸にちなんで、いずれも「江戸系の品種群」あるいは「江戸系」花菖蒲と呼んでいます。 『菖翁花』の学術的な存在価値江戸系の品種群の中で、最も基本になった菖翁の育成した品種群は、一番最初に育成されたので、江戸系の中でも特別扱いされて、特別に『菖翁花』と呼んでいます。菖翁花は歴史的、文化財的に価値の高いものとして貴重です。 本学では、『菖翁花』に属する品種が、最も古い最初の栽培品種の花菖蒲の起源と捉え、わが国のどの地域に自生していた野生のノハナショウブを使って育成したのかを知るには最も適すると考えました。そこで『菖翁花』の収集を行い、それらを鉢植えにして混ざらないように維持・管理し、形態学、生理学、および分子生物学的および歴史書から研究を行いました。 同時に、日本全国の野生のノハナショウブを収集して自生地ごとに分類、維持・保存して『菖翁花』と 分子生物学的に比較・研究を行いました。 その結果、2016年、「信州霧ヶ峰周辺と日光一帯に自生するノハナショウブから育成された」ことを初めて発見、発表しました(小林ら、2016)。 また、菖翁が育成した『菖翁花』は、菖翁自身の著、『花菖蒲培養録』、『花菖蒲花銘』や『菖花譜』にも、「信州や奥州(日光周辺と考えられます)で採集したノハナショウブの種子をまいて育成した」ことが記載されていますので、科学的な知見と、と歴史書の内容が完全に一致しました。 野生のノハナショウブの学術的な価値本学では、約30年にわたって、信州・霧ヶ峰周辺と日光一帯のノハナショウブを当局の許可の基に収集し、同時に『菖翁花』と言われる品種を収集し、それぞれが混ざらないように、鉢植えで分けて維持・保存しています。これらの自生地のノハナショウブは、江戸系品種の起源になったものとして重要であるので、「遺伝資源」として末永く維持・保存する意義があります。 その一方で、『菖翁花』と呼ばれている品種は、現存している品種は約24品種です。江戸時代に菖翁は約200品種を育成したので、ほとんどの品種は絶滅し、現在ではごくわずかしか残っていないことになります。 そこで、『菖翁花』の育成基になった、『信州・霧ヶ峰と日光に自生するノハナショウブの遺伝子を持つ品種を『菖翁花』とみなす』こととして、この観点からこれらの地域に自生するノハナショウブと、収集することができた『菖翁花』と呼ばれている24品種につき、分子生物学的な研究を行いました。 また、「江戸古花」と呼ばれる江戸系品種の中に、実は『菖翁花』があるのに、見過ごされている可能性も否定できなかったので、本学で入手した明治神宮・林苑を中心にして収集した「江戸古花」の84品種を用いて分子生物学的な研究を行いました。 これらの研究を分子生物学的な手法を用いて繰り返し検定を行った結果、80%以上の確率で遺伝子が一致する品種は以下の品種になりました。 その一方で、「五湖の遊(ごこのあそび)」、「雲衣裳(くもいのしょう)」および「都の巽(みやこのたつみ)」は、菖翁が育成したと言われていましたが、本学の研究結果では、分子生物学的にはいずれも60%以下の結果となり、科学的には「菖翁花」ではないことがわかりました。ハナショウブの栽培品種は、株分けで増やして継代受け継がれるので、この時点で異なった株と混入した可能性、あるいは種子がこぼれてその実生株が維持された可能性があります。また、菖翁が肥後に贈った品種の中に「雲井」と「松ヶ枝」がありますが、科学的に菖翁が育成した株の品種ではなかったことが、科学的に明らかになりました。 本学で30年間にわたって行ってきた、形態学、生理学、および分子生物学的な研究の結果、24品種の「菖翁花」は、19品種が信州・霧ヶ峰と日光に自生するノハナショウブの遺伝子と合致したことになり、科学的に「菖翁花」ということになりました。 その一方で、本研究により『菖翁花』であるとされてきたにも関わらず、科学的に『菖翁花』ではないと判断された品種は、①「五湖の遊」 ②「雲衣裳」 ③「都の巽」 ④「雲井」 ⑤「松ヶ枝」です。 これらの5品種は、明治神宮・林苑に植えられていたものを研究に用いたので、『菖翁花』ではなかったのですが、明治神宮・林苑の導入先が堀切の小高園であったことから、『菖翁花』を含めて小高園で育成された品種、あるいは周辺の別の花菖蒲園で育成・栽植されていた品種に由来する「江戸古花」だったことになります。 また、同時に行った 「江戸古花」の84品種については、『菖翁花』に該当する品種は見出せませんでした。 「宇宙」の花器官は弁数、形態、構造が非常に複雑で、かつ花容が「ひねったように」なります。本ホームページに掲載したように、一様に同じ形態をしたものがありませんので、写真撮影には様々な角度からの画像が必要です。 通常、花菖蒲は開花後に株が分枝して、株の基部から翌年の開花株を成長させていきますが、「宇宙」の場合は、地下茎の分枝性がほとんどないので、極めて弱く、当年開花させると、翌年の分枝株が伸長成長しないことが多く、その場合には絶えてしまいますので特に注意が必要です。 このように、『菖翁花』に該当する品種は、地下茎の分裂能力や発根、萌芽能力が非常に弱いので、株の劣化が著しく、維持・保存が非常に難しいです。 そこで、『菖翁花』のような弱い品種を維持していくためには、花蕾が形成されても敢えて咲かせないようにして株の充実を図るか、株分けはこれまでのバイブルのように、敢えて3年に1回の株分けは行わないようにします。 現在、本学ではこのようにして株を充実させ、栽培法の確立に向けた研究も行っています。約30年にわたって花菖蒲の古花の品種の維持・管理ができているのは、このようにして「株の生育状態に合わせた管理法」を確立しているからであると考えています。 なお、「宇宙」に似た、「新宇宙」と称する「品種名の付いた」江戸古花があります。こちらは品種名が付いていますので、本ホームページには紹介しています(実生の場合には、品種名とはみなされません)。この品種は、「宇宙」とは一見似てはいますが、このページの「宇宙」のように花被片が大きく波打つことはないようです。 約30年余りをかけて、江戸古花の栽培品種( 『菖翁花』を含む)と、日本全国を歩き回って野生のノハナショウブを収集し、本学で株ごとに分けて維持・保存をしてきた成果でした。 |
| 文献 | : |
|
| 研究論文 の一部紹介 |
: | 江戸系の花菖蒲品種群はどうやってできたのでしょうか?栽培種の花菖蒲は、菖翁が野生のノハナショウブから育成したことは本人の著書により知られています。では、いったいどこに自生するノハナショウブから育成されたのでしょうか?長年の謎になっていました。 現在、『菖翁花』の育成基になった、野生のノハナショウブは地球規模の環境変異により自生地での乾燥化が急速に進み、減少しているか、ほぼ絶滅寸前です。 |