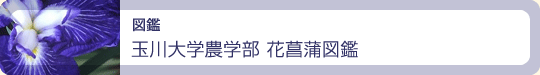5月初旬の栽培管理法
5月初旬から中旬にかけては、いわゆる「五月晴れ」となり、晴天が続き乾燥した日々となります。この時期は、2月に花芽分化をした花芽が発達をする時期で、特に花芽の伸長の時期にあたります。
毎日の水やりを欠かさずに行うと、写真のように葉が伸長してきます。潅水量を増やした分、伸長量が増え、1日で5〜10cmも伸長する個体もあります。

この写真の場合は地面に鉢を置いています。すでに緩効性の肥料をあげているので、施肥は必要ありません。葉が伸長した分、根張りも良好となります。葉が黄緑色の株もありますが、特に肥料は施さないようにします。
個人的には、朝、昼、夕方の3回に分けて1鉢ごとにたっぷり与え、水が引いた後、再度水をあげるようにすれば鉢全体に水分が十分に行き渡ります。
水やりの方法
水は株元に向けて行うことが重要です。葉に水をかけても全く意味がありません。
底面から潅水を行っている、あるいはプールなどの水にはった場所で管理を行っている場合は特に水やりは不要ですが水温が高温になやないように気を付けます。
鉢中の水がしみ込んでから、再度水をあげるとほぼ完全です。園芸学的には、鉢中の土全体に完全に水分を行き渡らせることになる意義があります。本学では有機質肥料を用いていませんので根腐れの心配はせず、39年間株をキープしています。
花芽の伸長と発達
葉が屈曲することがありますが(アコーディオンのように)、これは伸長している証拠です。いったん、縮んで水分を吸収することで再度伸長します。
花芽となる花茎は、葉の間から太い茎が上がってきます。

葉が屈曲しても問題ありません(左の矢印の部分)。いったん、伸長しかけた葉は屈曲しますが、水分を吸収すると一気に伸長します(右の矢印の部分)。
この写真では、すでに50cm以上になっています。
右の写真で、黄色丸の部分は、株元が太く、丸みを帯びています。これは花茎といい葉とは異なり、中に発達した花芽が入っています。水やりを行うにつれて花芽は花被片などの花器官を発達させながら上部へと伸長していきます。
同じく右の写真で、水色の丸は、平たいので花芽は入っていません。これは葉となるものですが、水を行うことで上に伸長し、黄色の花芽が発達している花茎の伸長に、養分を転流させる重要な役割を果たしています。すなわち、花芽の発達を助ける役割を担っていることになります。
なお、この時期に、花芽や葉中にヨトウムシなどの害虫の食害を防ぐために、浸透性の薬剤散布を行って予防すれば、花芽の発達に影響が少なくなります。