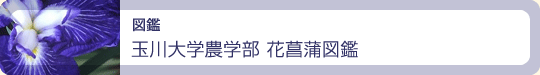おとめ
乙女
Otome
| 伊勢系 | 【花容】垂れ咲き 【英数】三英 【花色】薄桃 【開花時期】6月上旬 2014年は6月20日開花 |
| 分類 | : | 伊勢系で垂れ咲きの三英花です。 |
|---|---|---|
| 外花被 | : | 形状は丸弁で、大きく軸方向に下垂します。周縁部はゆるやかに波を打ったようになり、肩部は内巻きで縮緬状構造が発達します。花被片表面にも細かい縮緬状構造が見られます。花色は淡い桃色の地で、紅紫色のごく細い維管束(脈)が周縁部に向かって伸長します。アイは少し小さめで、先端部は周縁部に向かって小さく伸長します。アイの周辺は白色で、その周辺部はやや濃い桃色になります。 |
| 内花被 | : | やや幅の広いひら状で、軸に対して斜め上に伸長します。周縁部はわずかに内巻きで若干のフリルが認められます。花色は外花被片と同様の淡い桃色です。内花被全体にわずかな縮緬状構造が見られます。 |
| 花柱枝 | : | 太く短く、内花被片と同様に軸方向に斜め上に向かって伸長します。基部はわずかに黄色を帯びた白色です。周縁部に行くにつれ徐々に淡い桃色となる場合があります。先端部で2裂開し、四角、もしくは先端部がややとがった三角状のずい弁が発達します。ずい弁は内花被片と同じように、軸方向に斜め上に向かって伸長し、やや内巻きとなり、先端部には鋸歯(くも手)が発達します。ずい弁の花色は花柱枝よりも濃い桃色です。 |
| 備考 | : | 1904年以前に育成された伊勢系の古花であると言われています。伊勢系の古花品種は早咲きが多いのですが(6月初旬)、本学では鉢植えで6月中旬の開花となりました。草丈は50~60㎝で花茎は細く、葉幅も狭いです(1~2㎝程度)。花被片は開花と同時に軸方向に穏やかに下垂します。開花当初には縮緬状構造や、縮緬状構造が重なって「襞状」になり、花被片に陰影が生じます。開花後2日目には穏やかに花被片の細胞が肥大成長して平滑となり穏やかに下垂します。3日目には周縁部の細胞から崩壊して、結果的に花被片全体は乾いて花茎の先端部に残ります。花色も開花当初は濃い桃色ですが、次第に淡い白色になります。 このように、花の開花が進むのに伴って花被片の形状や質が変化する形質は、伊勢系の古花品種に特徴的で、古くからの鑑賞法として「花の芸」を楽しむ独特の文化が発達しました。このような鑑賞文化は、肥後系の古花品種でも見られます。 したがって、そのような「花の芸」を観賞できるような形質を持つ品種が、伊勢地方で発展したものと考えられています(トントン花の項を参照)。 花被片の厚さが薄いので、「室内での鑑賞」が基本です。屋外で栽培すると、花被片は風雨に弱い構造なので、雨水に濡れた部分の細胞が崩壊し、色素が抜けた状態になります。また、昨今の地球規模の温暖化により、高温が続く日には花被片のしおれの速度は早くなります。この写真は、開花2日目のもので、最も花被片が大きく伸長した状態を示しています。 「乙女」は、伊勢系の古花の中では最も「目に映えるような桃色が発達する品種」と言われています。この形質は、昭和に入って育成された江戸系や肥後系の「桃色の新花」の品種育成にも大きく貢献しました。「伊勢系の新花」では、「美吉野」、「津の花」などが有名な品種です。 伊勢系の古花は、室内での鑑賞用として鉢植えに向くように育成されたので、屋外での栽培、観賞にはやや不向きでした。そこで、戦後に花菖蒲園の造成がブームとなった際には、屋外で花菖蒲園に植え付けても栽培が容易で、かつ伊勢系の持つ花容と桃色の組み合わせが優れる「伊勢系の新花の品種群」が発展しました。花容と桃色の組み合わせを見て、ハナショウブに興味を持つきっかけを作った人も多くいるようです。 「乙女」は、古花としての観賞価値に加え、育種素材としても維持・管理が必要な品種ですが、根茎や根の発達程度も少ないので無理な株分けは行わずに、株の維持にあたっています。特に、昨今の地球規模の温暖化により、夏場の猛暑で根や根茎の発達が抑制されないように注意する必要があります(夏場の作業)。 |
| 参考文献 | : |
|