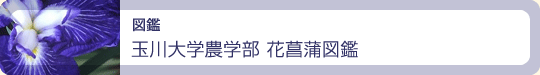つのはな
津の花
Tsu no Hana
| 新花(伊勢花容) | 【花容】垂れ咲き 【英数】三英 【花色】白地に紅紫色の砂子(花色の濃さには年次変動があります) 【開花時期】6月中旬 2025年は6月19日開花 |
| 分類 | : | 垂れ咲きの三英花で、冨野耕治氏が1958年に育成した品種です(新花、伊勢花容)。 |
|---|---|---|
| 外花被 | : | 丸弁で、被覆片の厚さは薄く、開花当初はやや平滑で軸方向に垂れ下がりますが、開花が進むにつれて周縁部は波を打ったようにフリルが入り、大きく軸方向に内巻きになります。 花被片の表面には非常に細かい縮緬状構造が多数発達します。花色は白色の地で紅紫色の砂子(砂をまいたように粒状に見える)が入ります。遠くから見ると全体的に桃色で、花被片の下部が影になると青紫色に見えます。また、紫色の筋が入ることがあります。 花被片の周縁部は、白色の細い覆輪(糸覆輪)が入ります。 |
| 内花被 | : | 形状は幅の広いさじ状でやや内巻き、細かい縮緬状構造となります。軸方向に直立、あるいは斜め上に立ち上がります。花色は桃色で細い赤紫色の砂子が入り、しばしば白色の筋が入ります。 |
| 花柱枝 | : | 軸方向に立ち上がります。中心部は白色で、先端部は2列、あるいはそれ以上に裂開して大きく見える幅の広いずい弁が発達します。ずい弁は軸方向に垂直に立ち上がり先端部は細かい鋸歯が入ります。ずい弁は裂開するので、花器官の中心部は複雑な構造となります。花被片は赤紫色の砂子模様が入り、白色の筋が入ります。 |
| 備考 | : | 冨野耕治氏により1958年に育成された品種です。戦後に育成された新花の品種です。伊勢系の古花のような形質を保有しているので、伊勢系の品種同士で育成したと考えられる花容です(伊勢花容)。 伊勢系の古花品種は外花被片が大きく垂れることから、鉢植えで観賞することが多いですが、本品種は花菖蒲園でも観賞できるように、比較的丈夫で群がって鑑賞してもすぐれるように改良されたようです。花径は18cm程度、花茎は40cmで他の品種よりも低く細くなります。 伊勢系の品種は、外花被の垂れ方によって、傾斜型に垂れる「富士型」、丸抱え型に垂れる「地蔵肩型」、直線型に肩を張ったようにして垂れる「怒肩型」がありますが、本品種は「怒肩型」に近い形状をしています→花の品種改良の日本史を参照。 ただし、これらの分類は、開花が進むにつれて変化するので、必ずしも厳密な分類とはいえない面があります(2列目から3列目、Tabuchi and Kobayashi, 2024)。 伊勢系の品種には、本品種のような伊勢花容、または伊勢系品種の桃色は観賞価値が高いとみなされて、品種改良が行われた結果、類似品種が多く存在します。 花色の濃さの程度は様々で、年次変動や株間変異の他、日陰で栽培すると濃くなりやすい傾向があります。花被片の形態(内花被片が幅広く、ずい弁は直立してしばしば複数になるなど)、花容、縮緬状構造(非常に細かい構造が多数存在する)の違いなどで区別します。 本ホームページの最初の4枚は濃い桃色ですが2,3列目は淡い桃色になり、3列目のように晴天時には白色に見えますので、「津の花」の場合は、内花被片が幅広く、大きく軸方向に立ち上がることで他の品種と区別がつきます。また、3,4列目の場合には、外花被片の周縁部に白色の細い糸覆輪が形成されます。濃い桃色の場合に急速に開花が進むと周縁部は青みがかり(花被片のいわゆるエージングは、周縁部から始まっていきます。その際に特有の酵素が発現します)、直ちにしおれるので、白色の糸覆輪は認められません。 外花被片の細かい縮緬状構造と内巻き、ずい弁の裂開が多いことも特徴です。 育成者の富野は、これらの形質を総合して「狂い性」が良く出る美花と表現しています。 写真撮影:最初の4枚は小林孝至(本学・博士課程3年)、2,3列目は2025年に筆者が撮影したものです。 |
| 参考文献 | : |
|