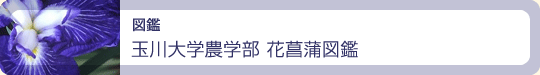まいこまち
舞小町
Maikomachi
| 野生(例外) | 【花容】平咲き 【英数】三英 【花色】白地に青紫色の細い筋が入る 【開花時期】6月下旬(2021年は6月15日開花) |
| 外花被 | : | 丸弁で水平、もしくは開花が進むにつれて、先端部がやや下垂する平咲きの品種です。アイの周辺部から、濃い紫色の非常に細い筋が先端部に向かって伸長します。 |
|---|---|---|
| 内花被 | : | さじ状で非常に短く、軸方向に向かって直立します。青紫色は目立ちます。 |
| 花柱枝 | : | 内花被片と同様に、非常に短く、白色です。先端部は裂開して軸方向に垂直にずい弁が発達します。ずい弁の先端部は鋸歯状です。 |
| 備考 | : | 山形県・長井地方に古くから伝わる品種で、昭和37年に発見され、昭和63年に長井市によって命名された品種です。長井市の「あやめ公園」で保存されています。この品種の特徴は、外花被片が白く、内花被片が青紫色で、両者の花の色が2色に明確に分けられることで、一般には「二色花」と呼ばれる典型的な花色のパターンを示す代表的な品種といえます。 明治43年に開園された「長井あやめ公園」で保存されていた花菖蒲の品種の一つで、長井市の近隣、飯豊町萩生(いいでまち・はぎう)周辺のノハナショウブ由来の花菖蒲であることが、本学の研究で科学的に明らかになっています。これらのノハナショウブは、1980年代に本学と現地との間で精力的な探索が行われ、貴重な野生のノハナショウブが本学に保存されています。現在では、遺伝子侵食により絶滅しておりますが、このピュアな野生種のノハナショウブ同士で交配が重ねられて本品種などが育成されたことが、本学の研究で明らかになっています。 「長井小紫」と「長井古紫」(リンクおお願いいたします)を参照ください。なお、昭和37年に愛好家の団体に発見されて以来、町おこしとして発展して知られるようになった品種群で、現在では「系」とはせず、長井古種、あるいは長井古種に何かの系を交雑して出来たものを、「長井系」として区別しています。長井市では「長井古種」をいくつか選定して「あやめ公園」に栽植しています。 |
| 参考文献 | : |
|