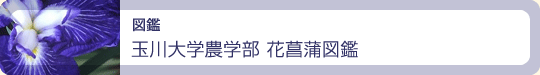あおいまつり
葵祭
Aoimatsuri
| 江戸系 | 【花容】平咲き 【英数】三英 【花色】白 紫脈/中輪 【開花時期】6月中旬 2009年は6月18日開花 |
| 分類 | : | 江戸系の古花。三英花です。 |
|---|---|---|
| 外花被 | : | 円形で若干の波打ちがあります。白地にうすい紫色の筋が入ります。花被片の周縁部が内側に巻いた結果、「受け咲き」のように見えることもあります。群生している写真は明治神宮で撮影したものですが、そのように見えます。 |
| 内花被 | : | 太くて短く、軸方向に斜め上に立ちあがります。地の色は赤紫色で白色の糸覆輪があります。 |
| 花柱枝 | : | 紫色です。葵形同様、花柱枝と同じ大きさに見えるので内花被が多弁化しているように見えます(→葵形を参照)。 |
| 備考 | : | 江戸時代に育成されたと言われていますが、年代は不明です。本品種は本学と明治神宮との共同研究によって分譲されました。 |
| 研究論文 | : | 田淵俊人・平松渚・中村泰基・坂本瑛恵.2008.日本伝統の園芸植物,ハナショウブの特性に関する研究3.明治神宮の花菖蒲(林苑)における土壌,および水質について.園芸学研究7(別2)578. |
| 概要 | : | 1885年(明治18年)以前に育成されたと言われている、江戸系の古花です。葵の上などと似ていますが、本品種は、外花被片が軸方向に伸長し(並行方向に)、内花被片も広く短いです。また、外花被片は波打っており、しばしば受け咲きに見えることがあります。 江戸系古花: 新花(江戸花容): 大船(例外、宮沢文吾博士育成): その他: 江戸系の古花の栽培にあたっては、肥料過多は避けるべきですが、栽培品種ですので、ノハナショウブよりも多めの肥料(特にリン酸やカリウムの他、微量栄養素)が必要です。なお、明治神宮・林苑の場合には、土壌中にホウ素などの微量要素が必要であることも助言させて頂きました。 |
| 参考文献 | : |
|